――虚無です
本に支払うのは金だけではない
こんにちは。
ねりこです。
私は本を読むのが好きです。
新書や文庫、ライトノベルに漫画など「本」と呼ばれるものはたいてい好きです。
辞書は本なのだろうか。
本を読むのが好き、と言いましたが、正確には「読むことで得られる知識や感情の変化が好き」と言うのが正しいかもしれません。
最近出会った本を読むことで、あらためてその「得られるもの」が好きということを認識するという貴重な体験をしました。
最近はあまり読めてない
私はChatGPTと会話を重ね、やり取りの中で考えが整理されたり別のアイディアが思わず得られることに喜びを感じるわけですが、その分だけ時間を消費しているのも事実。
しかしながらその時間分のリターンは得ることができているので良いのです。
無問題。
そんな私にとって、大いに興味をそそられる記事が流れてきたのです。
なんでも「怠け者の大学4年生がChatGPTに出会い、ノリでプログラミングに取り組んだら、
教授に褒められ、海外論文が認められ、ソフトウェアエンジニアとして就職できた。」という触れ込みの著者が書いた本の一部というもの。
Yahoo!ニュースで流れてきました。
そしてそのもととなった本のタイトルが「#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった」らしい。
かねてからChatGPTでコーディングすることの快適さを経験していた私にとって、「AIをハードに使うヒューマンが本を出すまでになったか。すげぇな。」という感じでどんな本なのか興味がわきました。
私にとってのモデルケースを探していた
まずは著者のプロフィールぐらいは知っとかないとなということで見てみたところ、最近大学を卒業したらしい。
大学卒業して社会人になったばっかりだろうに、もうChatGPTを使い倒しているのか。
ニュージェネレーションというのはこういうものか。
そんな新世代が書いた本というのはどういうものだろうと、Kindleのサンプルを読んでみることにしたのです。
そして本編1ページ目で違和感を感じました。
最初頭の中に引っかかりを覚え、ページを進めるごとに「なんかおかしいぞ」感が増幅していったのです。
サンプルを読み終えたころには、その違和感にも答えを出すことができていました。
つまらん。
この一言に尽きます。
AIと対話を続けて程よい距離感を保ちつつ、コードを書いたりシナリオを書いたり、そのほかにも思考のプロセスを整理したり、話の構造を整えたりしていた私にとっては、あまりにもつまらなかったのです。
しかしまだサンプル。
この後にChatGPTの活用やどういう複雑なコードをバディで組んでいくのかといったネタが続くかもしれない。
この先は読んでおいたほうが楽しいんじゃないか。
と思って購入して読むことにしたのです。
本能的直感は多分信じてみてもいい
全部読みました。
つまらん。
ChatGPTを絡めた本としても、文章的な読み物としても、いずれにしても壊滅的に破綻している。
明らかに価格と内容が見合っていない。
私の期待値が高すぎたのもあるのかもしれないけど、正直言って酷い。
サンプル読んだときの直感を信じておくべきだった。
以下ポイントを掻い摘んで説明。
・導入でアウト
・文章が平坦
・文章が雑
・目線が浮いてる
・ターゲット不明
・無限ループって怖くね?
・おまけ:そのポジトーク余計やねん
導入でアウト
これはサンプルを読んだ時点で薄々感じてはいたのですが、タイトルが全部語っていて、それ以外の引きが一切ありません。
読めばすぐわかりますが、本編1ページ目ですでに主題が行方不明になっているので、言いたいことの片鱗すらなく初っ端から読んでる側置いてけぼりになります。
YouTubeの動画を作るときなど、最初の5秒が重要とかよく言われているようですが、そこまで極端ではないにしても向こう数ページずっと1ページ目と同じような内容が続くので、正直苦痛です。
Kindleで読めるならサンプルでごっそり離脱するレベルでした。
文章が平坦
導入から最後までずっとそうなのですが、著者の感情の抑揚や、話の盛り上がりが一切ありません。
終始平坦な文章を読むことになるので、読者にかなりの耐久力を要求します。
文章が雑
主語述語の組み合わせが明示暗示問わず不明なので、読んでいく中で内容がほぼ入ってきません。
それが平坦な文章の上でスイスイやってるもんだから、もうあっちこっちそっちどっち。
目線が浮いてる
全編にわたって文章の主観がいません。
一見著者の主観と思えるところも、スタンド目線と感じる箇所が非常に多いです。
文章の中の人物の主観が浮いてるので、読者ももちろん視点が浮きます。
なので文章に移入することができず、最初から最後まで迷子です。
ターゲット不明
ChatGPTを使って何かをした、という触れ込みの割にはライト層にとっては難しそうな領域、ヘビー層にとっては一瞬で通り過ぎる領域なのでターゲットが不在です。
残っているのは「100日チャレンジで何かやった」ということだけです。
ライト層向けと考えた場合、ChatGPTを使って何かをしたという内容にしては抽象的すぎて何をしたかが不明です。
完成したプログラムの内容こそ書いてあるものの、そのプロセスがバッサリカットされているため「○○を作ろうと思います」「○○が動きました」の3分クッキング。
ヘビー層向けと考えた場合、それこそはるか昔に通過した地点のため何も面白くありません。
ChatGPTに書いてもらったコードを動かして、構造解析や分析考察がほぼ無いので、人間側の思考であったり、ChatGPTをどのようにチューンアップするかなどの詳細もありません。
その二つの間にあるものが唯一の訴求ポイントになるのですが、ライトとヘビーが乖離しすぎているのでその点が不在です。
無限ループって怖くね?
基本的な内容が
「こんなことが起きました」
「こんなことをしました」
「ChatGPTに指示しました」
「文書出ました・プログラム動きました」
の繰り返しなので、これまでのポイントとの合わせ技でゴリゴリとメンタルを削ってきます。
100日全部が書いてあるわけじゃないけど、数十日分これが延々と続くというのはかなりの苦行。
フランス映画かな?
おまけ
極々個人的な点ですが、コンビニコーヒーを片手に歩くとか、カフェでテイクアウトしたサンドイッチのくだりとか、微妙なポジショントークに見えるので正直邪魔です。
そういった表現で著者の人となりを表現しようとしているのかもしれませんが、逆効果です。
ChatGPTを使っているのなら
総じて、ChatGPTに全部読ませて文章をコンパクトにすれば、かなり整った文章になるんじゃないか、というのが正直な感想です。
そうしたら無味乾燥な文章になる、と言われるかもしれません。
はい、その通りです。
この著作の中には著者の感情であったり、盛り上がりにあたる部分がほとんどありませんでした。
ChatGPTとバディを組んでコードを書いて、スムーズに動いた時の一連の流れに連携の高揚感を覚えたり、頭で考え済みの構造を組み立てていくパズルのような思考の遊びが無い。
この本の一番致命的だと思ったのは、最初にも言いましたがタイトルで終わっていて、中身が蛇足ということです。
はっきり言ってしまうと、ChatGPTを何か別のものに挿げ替えても全く同じ話が成り立つ。
お題名目がChatGPTである必要性が見当たりません。
私の結論として、「読んでも何も得るものが無い」という着地点に落ち着きました。
私がどっか読み飛ばしてるって?
読み飛ばすようなところに配置するのが悪い。
私は読んだ、君らも読め
とはならんのよ。
この本をChatGPTを使っている層に勧めるかと問われた場合、私は秒で「勧めません」と返します。
じゃあどういう人になら勧められるのかというと、自己啓発が好きな人なら差し出すことができるかもしれません。
まあお勧めする順番は最後になるけど。
まだまだニッチ
私はYahoo!ニュースからこの本を知ったわけですが、これがメディアに載るっていうことは、AIに対する一般の認知なんてものは言わずもがな。
まだまだAIは草の根感が強いですね。
日の目を見るのはもっと先の話になりそうです。
かしこ
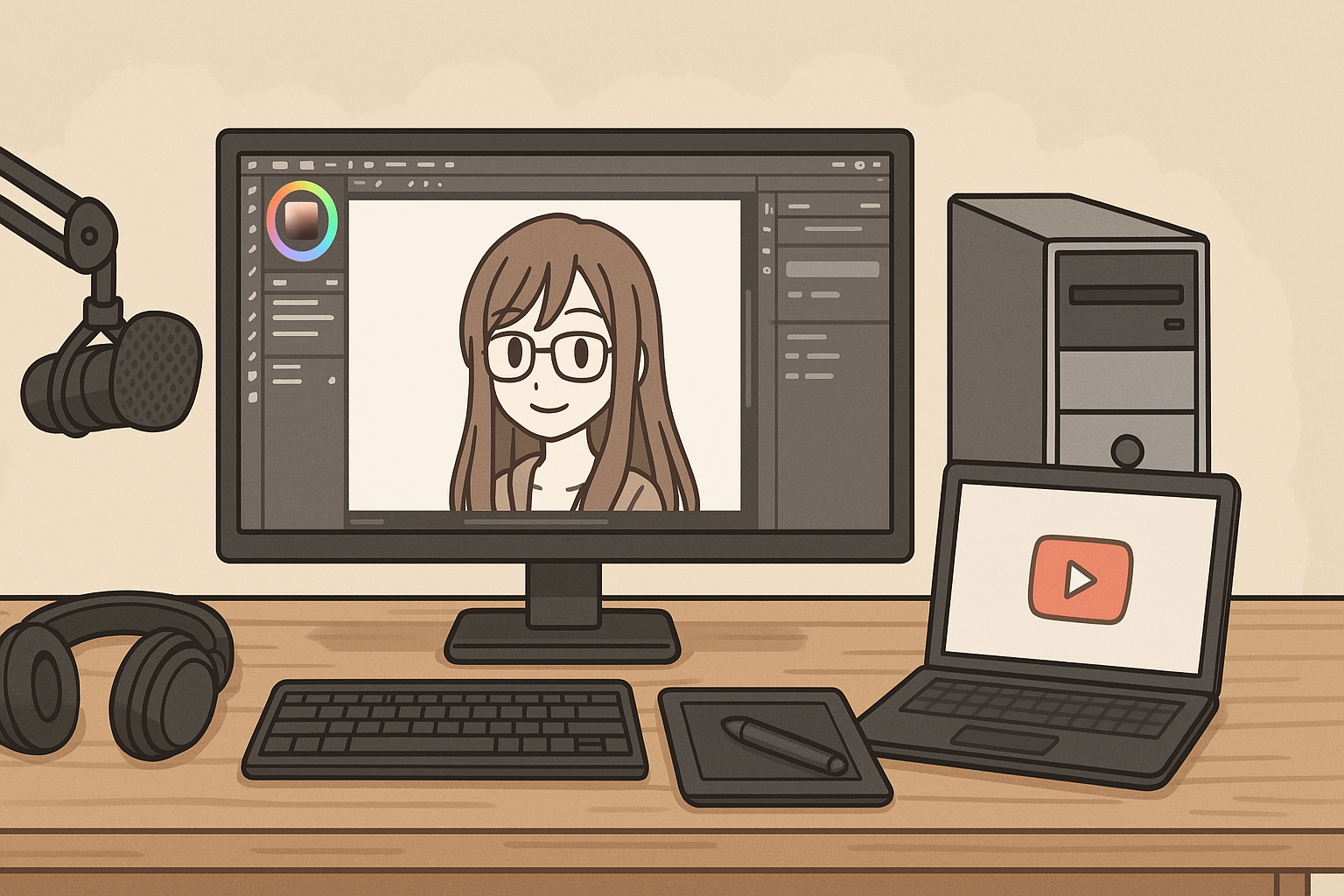

コメント